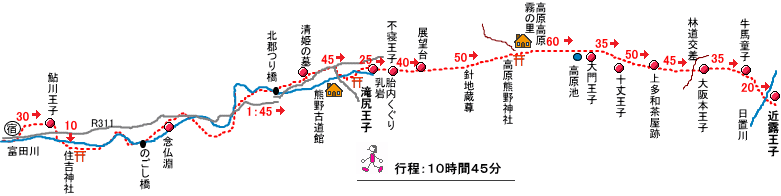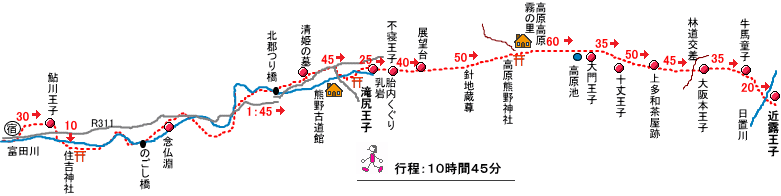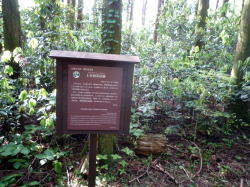6月6日(月) |
 |
 |
| 鮎川王子から近露王子へ |
| 今朝はやっと天気になり、青空も見えてきた。 |
| 私のまめは痛いが、大きなバンドエイドで保護したら昨日よりはましになった。ここまで来て、まめくらいで断念したくはない。 |
| なんとか頑張ってみよう。 |
民宿を出て、国道より左の坂を登る |
鮎川王子 |
 |
 |
この辺りの古道は、町の中、民家の間などあまり残っていない。 |
| 花折地蔵、千人供養塔などの案内があった。 |
| 道路沿いの鮎川王子から、鮎川新橋で右岸へ渡ると、鮎川王子の社殿が残る住吉神社へ着く。 |
| 鮎川新橋渡り右岸へ |
住吉神社 |
|
 |
川を離れ、登り坂となる。 |
 |
| 富田川は緩やかに蛇行する。昔、禊をしただけのことはある、清らかで美しい流れだ。 |
| 川沿いに、キイチゴが沢山なっていた。一粒つまむと甘酸っぱく美味しい。ジャムにでもしたい。 |
| 住吉神社第3殿 鮎川王子の社殿残る |
この辺りも梅林が多い。 |
富田川沿いのキイチゴ |
| しばらくすると念仏淵に出る。後白河上皇の前世のドクロが松の根に刺さって沈んでいたという伝説が残されている。 |
| 川を渡る国道の高架の下をくぐり、北群(ほくそぎ)トンネルの上を巻いて、急坂を登る。 |
 |
 |
| 途中には、江戸時代の石仏や唐申塚が点在する。 |
| 道路を沢ガニが歩いていた。 |
|
富田川(とんだがわ) |
北郡(ほくそぎ)吊り橋渡る(車通行不可) |
| 今日は、行程に余裕があるとクマさんが言うので、のんびりとコーヒーブレイクなどしたが、ここまで少し時間がかかり過ぎたようだ。 |
 |
 |
| 清姫の墓があるこの地は、清姫の出生地だそうで、夏は黒髪をなびかせ川で泳いだそうだ。(清姫淵) |
| すぐ先に清姫茶屋やトイレもある。 |
| 滝尻王子まで、まっすぐ川を遡る。 |
清姫の墓 |
音の居モニュメント |
 |
 |
 |
| 熊野古道館 |
滝尻王子 |
世界遺産の碑 |
 |
やっと滝尻王子に着いた。予定より1時間も遅れている。 |
 |
| 一番の人気スポットだけあり、熊野古道館(案内所)、土産物店、大きな駐車場もある。 ここまでバスや車で来て、ちょと見て回る人たちが多いようだ。 |
| 土産物店 |
滝尻より山中へ |
滝尻より山道に入る |
| 滝尻王子だけは、ご朱印がもらえる。 |
| いよいよここから山道に入る。足は痛いが我慢できないほどではない。山道になれば、何とか頑張れそうだ。 |
| 滝尻からは、熊野の霊域の入り口といわれ、中辺路一番の難所、女坂、男坂、三越峠越えがある。ここより本宮まで19王子をたどって歩く。 |
 |
 |
女性がここをくぐれば安産すると言われる胎内くぐり、乳岩は、藤原秀衡夫婦が滝尻で産気づき、出産した男児を神のお告げに従い、岩の下に置いて熊野へ参詣した。 |
| 急いで戻ると、赤子は岩から滴る乳をのみ、オオカミに守られ無事だったという伝説が残る。 |
| 胎内くぐり |
乳岩 |
|
| 熊野の神の霊力を語る象徴といわれる。(神のお告げとはいい、生まれたばかりの子を置いて行くなんて) |
| 大阪から来て、滝尻までバスで来たという男性が二人、追い越していった。山中で人に会ったのは初めてだ。 |
 |
 |
| ここより本宮まで、番号道標が500mごとにある。緊急連絡先も書かれ、非常時には番号で確認が取れるようだ。 |
| |
不寝王子跡 |
№1番号道標(ここより500mごと) |
 |
剣ノ山経塚跡を過ぎると、展望台への急階段があった。登ってみたが、今日は霞んで見晴はよくない。それに木が茂って覆っている。 |
 |
| 緩やかに下って、高原へと向かう。見晴らしの良い尾根道で気持ちがいい。 |
| 険しい木の根道 |
|
石畳道を下る |
 |
木の急階段を登ると、針地蔵があり、民家のある高原へ向かう。 |
 |
| 高原熊野神社は、楠の大木に囲まれ、室町前期の建築様式を残す春日造りで、中辺路最古の建物といわれている。 |
| 針地蔵尊 |
|
高原熊野神社 |
 |
 |
初めての自販機 |
| 神社の先にある休憩所は、この山中で初めて自販機があった。冷たい缶コーヒーやポカリスエットが体に沁み渡る。 |
| おにぎりとゴボウスープで昼食休憩。クマさんが背負ってきてくれたオレンジが美味しい。 |
| 高原霧の里休憩所 |
棚田と果無山脈 |
|
| ここからは田植えが終わったばかりの棚田の向こうに、折り重なる果無山脈が素晴らしい。去年は、あそこを歩いたのだった。 |
 |
 |
| 旧旅籠通りの、急な石畳を登っていくと、こんな所にカフェがあった。横目で見ながら通過する。 |
| セッコクが咲いていた。 |
| 高尾山の花はどうだったかしら。 |
セッコク |
旧旅籠「亀屋」 |
 |
 |
登りきると、木立の中に高原池がある。平安時代、藤原宗忠が泊った「水飲仮屋」だとされる場所だ。 |
| 上り下りをくり返し、朱塗りの社がある大門王子跡を過ぎると、東屋があった。 |
| 山中には花は少なかったが、ガクウツギの白い花は多く見られた。 |
| 急坂を登り集落を抜ける |
高原池 |
|
 |
 |
 |
| 登りが続く |
ガクウツギが多く見られた |
大門王子 |
| 急に視界が開け十丈王子には、トイレもある。休憩にはよいところだ。さすが世界遺産。要所要所にはきれいなトイレがあるので安心できる。 |
 |
 |
| 小判をくわえて死んでいた巡礼者を供養したという小判地蔵を過ぎると、悪四郎屋敷跡がある。悪四郎山は巻いて行く。 |
|
十丈王子トイレ |
十丈王子跡 |
 |
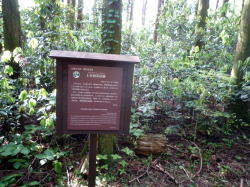 |
上多和茶屋跡はつづら折りの急登になる。9キロのザックは重く、肩が痛くなってきた。 |
| 上多和には、月が三体になって現れたのを見たという、「三体月」伝説が残されている。 |
| 小判地蔵 |
上多和茶屋跡(688m) |
|
| 林道を交差し、大阪本王子跡を過ぎ、下っていくと古道は国道をかすめ、牛馬童子バス停に出る。中辺路のシンボル牛馬童子は、箸折峠にある。 |
 |
向かいには道の駅中辺路がある。だいぶ時間が遅くなっているのでそのまま通過する。 |
 |
| 道は再び山中に入る。カメラを提げた男性が戻ってきた。道の駅に車を停め、写真を撮りに行ったようだ。 |
| 石垣の残る下り道 |
|
箸折峠 |
| この峠は花山法皇がここで昼食を食べた際、萱を折って箸にしたことが由来とされている。近露の名も、その萱から赤い汁が出て、「血か、露か」と尋ねたのが起源だそうだ。 |
 |
10分ほど下った時、クマさんが「アッ眼鏡がない!」「エッ~~」「箸折峠で休んだ時かもしれない?」ザックを下ろし、引き返した。あったそうだ。よかった。 |
 |
| 牛馬童子(道中のお姿とされる) |
|
水垢離(日置川) |
 |
 |
水垢離をしたという、日置川を渡るとやっと近露王子到着。 |
| 番号道標は№26まで来た。 |
| 長い一日だった。予定より大幅に遅れ、近露王子のすぐ前にある宿「月の家」に着いたのは、もう6時を廻っていた。 |
| 近露王子跡 |
創業100年民宿「月の家」 |
|
| 足もなんとか大丈夫だったが、疲れた。宿のご主人は古道歩きのアドバイザーのような人で、いろいろ注意を受けた。 |
 |
| 汗を流した後の夕食は格別。私は茶碗蒸しはあまり得意ではないが、ここの梅入り茶碗蒸しはおいしかった。 |
| 夕食後、七夕をするのでに短冊に願い事を書いてください。と言われた。願いが叶いますように。 |
| |
夕食(鍋は鹿鍋) |
| 同宿で、街道歩きをしているという男性は、もう主要街道はほとんど制覇し、今回熊野古道を始めたそうだ。私は、街道歩きよりやはり山歩きの方がいい。 |
| 明日はまた天気が崩れる予報。私達が予定していた赤木越ルートは止めた方がいいと言われ、正規の中辺路ルートで本宮へ行くことを勧められた。 |