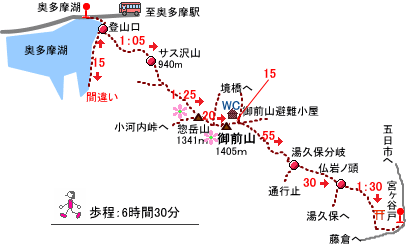| 御前山は10年以上前に、友人に当日の朝ドタキャンされ一人で登ったことを思い出す。長く急な登りが延々と続き、もう止めようか、もう止めようかと思いつつ何とか惣岳山へ辿り着いた。そこには一面カタクリが咲き、初めて見る群落に感激した。 |
| 今では、新潟の角田山、坂戸山などものすごい群生地をみているので、感激は少ないかもしれないが。 |
| 登山歴が長いJさんが、なぜか御前山へは行ったことがなかったそうで、カタクリの見頃に行くことにした。今回は、丹沢の達人もはるばる参加することになった。 |
| 連休の2日目、よい天気で奥多摩行き直通の電車はラッシュアワー並みの混雑。結局終点の奥多摩まで座れなかった。9割以上が登山客のようだ。 |
| バスを降りると、萌黄色の倉戸山は薄ピンクの桜が彩りを添え春たけなわ。 |
| 出だしから道間違い |
 |
 |
| 小河内ダム堰堤を渡り、多くの登山客の後をついて行った。(これが間違いの元) |
| だいぶ歩いたのに、なかなか登山口の標識が出てこない。 |
|
奥多摩湖と倉戸山 |
御前山登山口 |
| 大勢いた登山者もいなくなってしまった。これはおかしいのでは?地図を出して確認すると、登山口をだいぶ過ぎてしまったようだ。途中にサス沢山辺りに登る破線ルートがあったが、ふりだしに戻ることにした。10年前に歩いた記憶は、ほとんど消えている。 |
| 来た道を戻ると、堰堤を渡ってすぐに標識もあり登山口があった。これで30分以上ロスしてしまった。 |
 |
 |
もう次のバスの人達に追い付かれてしまった。気を取り直し急坂を上る。 |
| ここ2~3日暑いくらいの日が続き、一気に木々が芽吹いたようだ。 |
| ブナの若葉が、食べてしまいたいくらい瑞々しい。 |
| 急登の連続 |
ブナの若葉 |
|
| 急坂が続く。「10年前によく一人でこんな所登ったわね。」と言われた。本当に山を始めたばかりだったのに、よく行ったものだ。 |
 |
 |
| 1時間ほど急登が続いたら、少し平坦で展望が開けた所へ出た。サス沢山だった。奥多摩湖がよく見える。 |
| 時々ミツバツツジが目を引く。 |
サス沢山(奥多摩湖を望む) |
平坦な道(ヤレヤレ) |
 |
少し平坦な道で、ほっとしたのもつかの間、今度は岩場出現。 |
 |
| この辺りからカタクリが見られ始めた。下って来た人が「上はいっぱい咲いていますよ」と言われ、ワクワク。 |
| 今度は岩場 |
|
明るい防火帯 |
| しばし明るい防火帯の道になった。向こうに見えるのが惣岳山か。まだだいぶ先だ。 |
 |
 |
カタクリは下を向いて咲いているが、急坂なので下から見ると、中心のジグザグ模様までよく見える。 |
| 辛い急登が続く。 |
| 登りきった岩場の陰に、ワチガイソウが咲いていると教えてくれた人がいた。 |
| カタクリ(中心の模様もくっきり) |
急坂を登る人たち(振り返って) |
|
 |
帰って調べてみたら、ワチガイソウは花弁が5枚。これは、ヒゲネワチガイソウといい花弁は5~7枚で、標高の高い所に多いそうだ。 |
 |
| コバイケイソウの群落があった。ニリンソウも見られた。 |
| ヒゲネワチガイソウ |
|
コバイケイソウ群落 |
 |
カタクリ群落消えた! |
 |
| 惣岳山への最後の登りは、更に傾斜が増す。惣岳山到着。最初のロスを少し取り戻した。 |
| 山頂は10年前には、一面カタクリが咲いていて、よけて歩くようだったのに何にもない。 |
| 惣岳山最後の登り |
|
惣岳山(1341m) |
| カタクリは、山頂広場の周りの林の中にはちらほら咲いてはいるがそれだけだ。10年ひと昔とはいうが、こんなにも変わってしまったとは。 |
| 朝早くお腹もすいたので、丸太のベンチに腰をかけランチタイムにした。今日は暑くて、もうペットボトル1本、テルモスのお湯もここで使いきってしまった。 |
| 休んだら早速虫に刺された。この間まで寒さ対策だったのに、早くも虫よけ対策が必要な季節になった。 |
| 一度緩やかに下り、登り返す。 |
 |
 |
| 途中三頭山方面の展望がよい。 |
| その間にフェンスで囲ったカタクリの群落がやっとあった。 |
| カタクリは、増えすぎた鹿に食べられ減ってしまったそうだ。 |
|
カタクリ |
群落はフェンスの中 |
 |
 |
御前山も多くの人で賑わっていた。 |
| 今日は都レンジャーの人を多く見かける。パンフなど配布していた。 |
| 記念撮影だけし、トイレのある避難小屋へと向かった。 |
| 御前山(1405m) |
御前山避難小屋 |
|
| 避難小屋はガラス張りで新しくとてもきれいだった。 |
 |
 |
| ダンコウバイが咲く向こうには大岳山が見える。クマさんはあそこを歩いている頃かもしれない。 |
| 水場でヨゴレネコノメとコガネネコノメが咲いていた。コガネは初めて見た。 |
|
ダンコウバイと大岳山 |
コガネネコノメ |
 |
湯久保尾根 |
 |
| ここから展望のあまりない、長い湯久保尾根を檜原村へと下る。 |
| 日当たりのよい所にはスミレも多く、ヒナスミレ、エイザンスミレ、ケマルバスミレ、タチツボスミレなど見られた。 |
| 湯久保尾根を下山 |
|
ヒナスミレ |
 |
下山後のバスが1時間に一本なので、最初は早いバスに乗るつもりで早目に歩いていた。 |
 |
| 少し急ぎ過ぎたのか、Tさんが足がつってしまった。 |
| 湯久保南尾根コース通行止 |
|
モミジイチゴとヤマブキ咲く道 |
| 道端で休み、Jさんが持っていた漢方薬(芍薬天草湯)を飲み、梅干を食べて水分を補給し、湿布をした。運良く通った都レンジャーの人が、消炎スプレーを貸してくれた。少し休んだらよくなってきた。大事に至らずよかった。次のバスに乗ることに決め、ゆっくり歩くことにした。 |
 |
 |
大岩が見られるようになった。仏岩ノ頭も確かなことはわからなかった。 |
| 尾根を外れ、植林を下る。 |
| Tさんが、「モミジッ葉だ。おひたしにすると美味しいよ」と、奥さんのお土産にすると摘んだ。 |
| 巨岩 |
モミジガサ(モミジッ葉) |
|
| モミジッ葉はモミジガサといい、山菜の王者で抗がん作用もあるそうだ。ここでは摘む人もいないのか、沢山あった。 |
 |
 |
| ヤブレガサの新芽は天ぷらにしてもおいしいそうだ。Tさんはいろいろとよく知っている。 |
| |
ヒトリシズカ |
檜原村宮ヶ谷戸 |
| 古い神社を過ぎると、檜原村宮ヶ谷戸に着いた。思ったより人家も多く、新しい家が多かった。 |
| バスの時間までまだ30分はある。飲料水はほとんどなくなり、自販機もない。そしたら、Tさんがザックから、また冷たい飲み物をたくさん出してくれた。渇いた喉に冷たいジュースはとても美味しかった。 |
| でも、今回のように長い行程ではなにがあるかわからないし、ザックは軽いに越したことはないので、お互い荷物はなるべく少なくしたい。(これからはあまり気を使わないでくださいね。) |