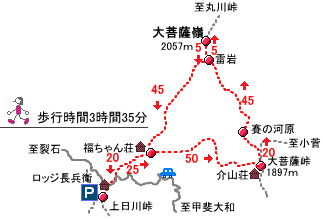| 今年は大菩薩のいろいろなコースをよく歩いた。私は今回で5回目。友人は6回も歩いている。 |
| それなら今年の〆はやっぱり大菩薩。と、忘年山行は大菩薩で決まり。 |
| Jさんが11月に下見をしてくれたが、12月下旬ともなると2000m級の山は冬山。様子がだいぶ変わって来た。上日川峠までの道路も塩山からは19日に閉鎖したそうだ。調べ直してくれたら、甲斐大和からの道はまだタクシーで行かれるそうなので、急きょコースも変更した。 |
| アイゼン持参で、ポピュラーな上日川峠からの周遊コースになった。 |
| 遠来の友 |
 |
 |
| 今回は、忘年山行をいつも楽しみにしていてくれるSさんご主人が、行けなくなってしまい残念だ。 |
| だが、久々に新潟から上京したS夫妻が加わった。賑やかになり、忘年会も盛り上がりそうだ。一緒に歩くのは6~7年ぶりになる。 |
|
上日川峠(ロッジ長兵衛) |
明るい尾根 |
 |
 |
甲斐大和の駅に降りると、タクシーが横付けになり、白手袋をした執事のような運転手さんが待っていた。 |
| 標高が上がると、路肩には雪が残る。富士山には少し雲がかかるが、天気は快晴。車は注意深く登っていく。 |
| 富士見荘 |
♪あ~たまを雲の上に出し♪ |
|
| 上日川峠はマイナス6~7℃。それでも歩いていると、体は暖かく、福ちゃん荘に着いた時は上着を脱いだ。 |
| 沢は凍り、日影は雪も凍りつき滑りやすい。下りはアイゼンが必要かもしれない。 |
 |
 |
| 大菩薩峠に近くなると、雪を踏む音がキュッキュッとする。 |
| 想像はしていたが、遮るもののない峠は風が冷たい。急いで上着を着る。 |
|
青空とシラカバ |
大菩薩峠 |
 |
やっぱり寒かった! |
 |
| 2000m級の山は、この間の里山とは大違い。 |
| 歩いている方がよいのではと、歩き始めたが、吹きさらしの尾根上は寒い寒い。 |
| 奥多摩方面 |
|
南アルプス |
| インナーダウンを着こむ人、マフラーで顔を覆う人、耳当てをしたり、手袋も2枚重ねたり、急いで防寒対策。 左頬は、射すように冷たくなった。手袋を重ねた左の指先が、ジンジンとしてくる。 |
 |
それにしても素晴らしい展望だ。時々立ち止まっては、眼下の大菩薩湖、その向こうに雲から顔を出した富士山、南アルプスの真っ白な山並みを眺める。 |
| キンキンの空気は澄み渡り、冬だからこその大展望。 |
| 大菩薩湖と富士山 |
|
 |
 |
 |
| 妙見の頭へ登る |
介山荘を振り返って |
八ヶ岳 |
 |
妙見ノ頭を登ると、八ヶ岳が見えた。雪でキラキラ輝いている。 |
 |
| あまりの冷たい風に、「やっぱり忘年山行は里山だね。」「高尾山でいいね。」とか、軟弱者の凸凹山岳会は、もうめげ始めている。 |
| 賽の河原に下ると、避難小屋の近くは風があまりない。 |
| 賽の河原 |
|
大菩薩嶺 |
| この先風を遮る所はないかもしれない。 |
 |
 |
| 他のグループが、小屋の前でラーメンを作っていた。私達もここでお弁当にすることにした。 |
| 手袋をはずしてお箸を持つと、手がかじかむ。手袋をしたまま食べることにした。 |
| |
ナナカマド |
立ち枯れの木 |
 |
 |
風に耐えながらも、ナナカマドの赤い実はまだ残っていた。 |
| 日当たりがよいので、日向にはもう雪はないが、日影は凍っているので注意が必要。 |
| 大菩薩嶺へは行かないで、雷岩で待っているという2人を残し、他のメンバーで山頂まで行った。 |
| 雷岩 |
大菩薩嶺 |
|
| 山頂に向かう森の中に入ったら、風が遮られあまり寒くない。風がないとだいぶ違う。大菩薩嶺はまだ地面が真っ白だった。 |
| 雷岩に戻り、カラマツ尾根を下る。 |
 |
 |
| こちらは風もなく暖かく、ポカポカしてきた。皆途中で上着を脱ぎ始めた。 |
| 雪は少しあったが、アイゼンをつけるほどではなくよかった。 |
|
カラマツ尾根下り |
マユミの木には・・・ |
| マユミの木に、”マユミの実は初冬の貴重な小鳥さんの餌です。折ったり、取ったりしないでね”と注意書きがあった。 |
| 私達が上日川峠に着くと、いい具合にタクシーが2台スタンバイ。今回手際良く計画をしてくれたJさんは、帰りもちょうどよい時間にタクシーを呼んでくれていた。天目山温泉に向かう。 |
| 温泉で冷えた体を温めた後は、忘年会。山よりこちらの方を楽しみにしていた人達もいたようだが、大いに盛り上がった。S夫妻とは初対面の人もいたが、気さくな人柄はそんなことをちっとも感じさせず、すぐに馴染んでしまった。これからも機会を作って、どんどん参加して下さい。 |
| 皆さま、今年もお世話になりました。よいお年をお迎えください。 |